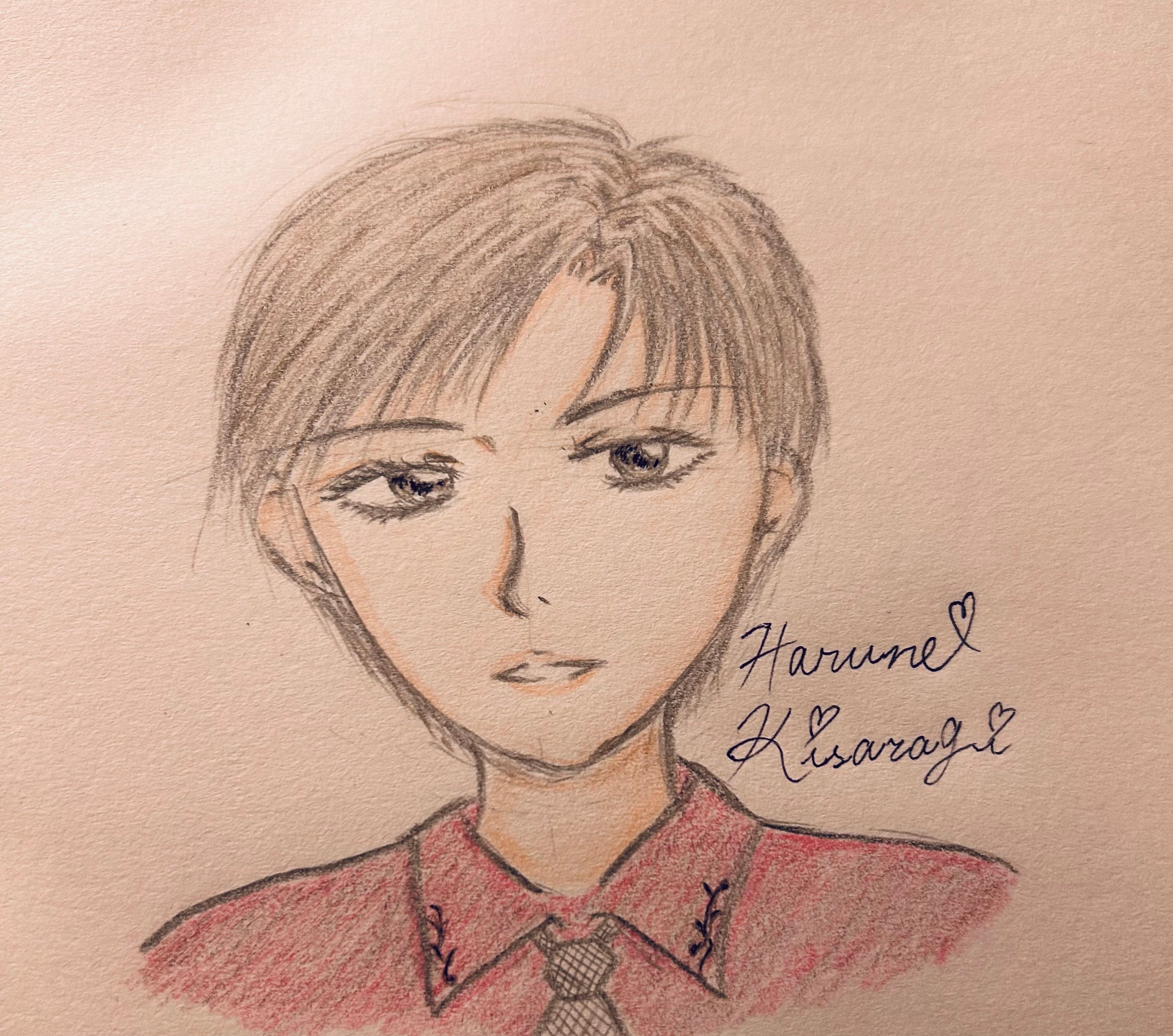by
シェア
唇が優しく触れ合ったかと思うと、8ページより
「……んぅ……」
すぐに友希の舌が、舞の唇をこじ開けて入り込んでくる。
深く絡み合う熱は蕩ける程に熱くて、甘くて――
胸がキュンと疼く度に、その苦しさのせいか少し苦味を感じる。
しばらくしてから、友季がゆっくりと唇を離して――
「相変わらず、苦くて甘いな。舞の唇は」
幸せそうに目を細めて微笑った。
「どっちがよ」
舞がツンとそっぽを向く。
けれど、
「舞」
痺れる程に甘い声で呼ばれて、振り向かないわけにはいかず。
「……何?」
「来年のハロウィンも、それ着て」
友希の熱を帯びた目と目が合い、
「もう二度と着ない」
舞はまた慌ててそっぽを向いた。
「店のお菓子、好きなのを好きなだけ食べていいから」
そんな友希の必死な声に、
「……考えておかないこともない」
はっきりノーとは言えない自分がいて。