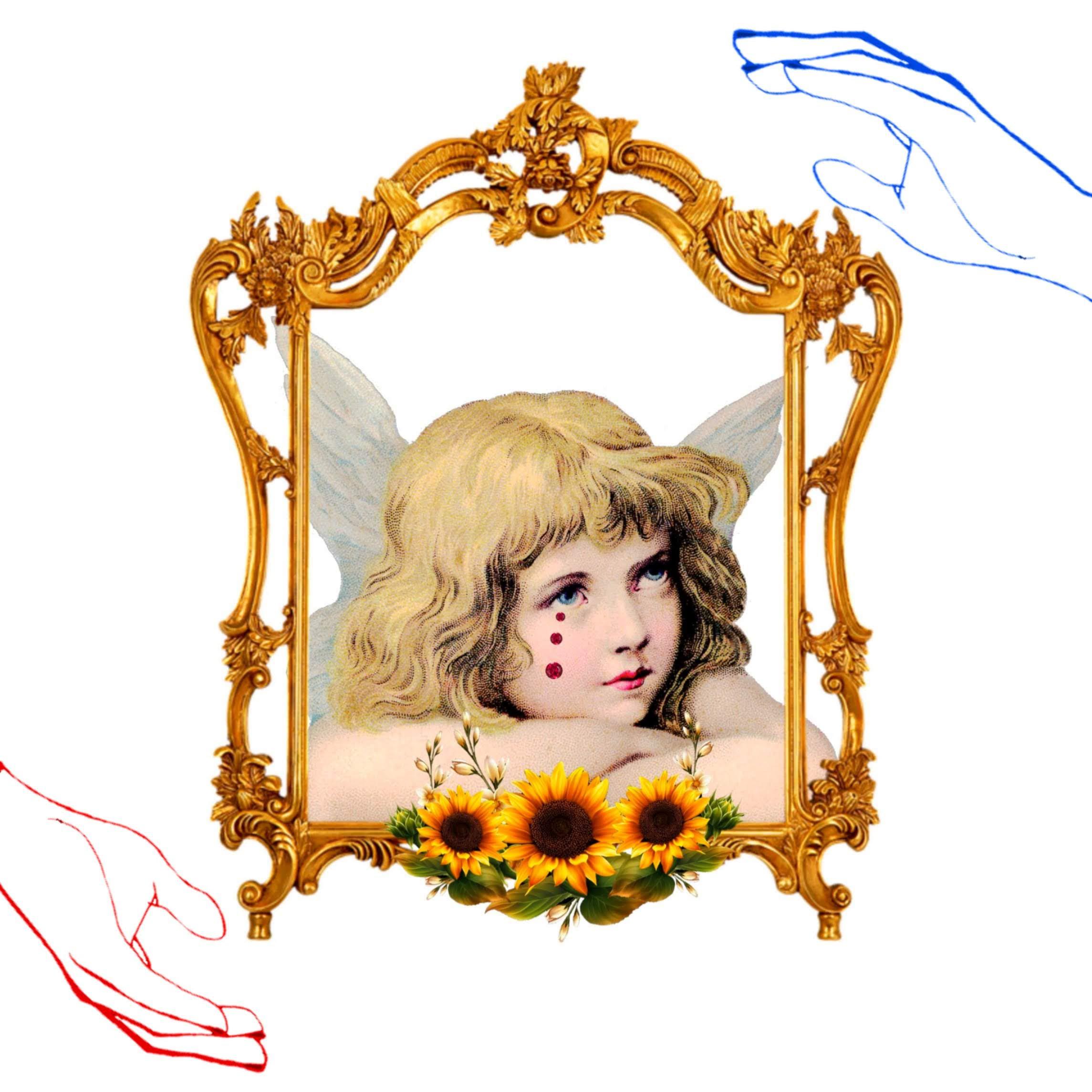僕の愛しい日鞠
春だけれど、まだまだ寒さが残っている。
正直、四季とかどうだって良いし、僕は春夏秋冬を愛でる心も、季節ごとに咲く花を愛でる心も持ち合わせていない。
だってそうでしょう?
僕は大切な大切な可愛い日鞠を愛でる心しか持っていないし、日鞠以外に「綺麗」と想えない事なんて当然の事だもの。
そんな僕だけれど、今日初めて、寒いのも悪くないって初めて想えたんだ。
「ひー君。」
長い睫毛を持ち上げて眠りから醒めた日鞠が、澄んだ美しい瞳にいつもみたいに僕の顔を映してくれたの。
それだけでも僕は毎日心が幸福感と充足感に満たされると云うのに、今朝の彼女は珍しく自ら躰を僕へと密着させて頬を桜色にしながら開口した。
「寒いから……ひー君の体温が気持ち良い。」
僕の胸元に頬を摺り寄せてそう放った日鞠に、心臓は容易に奪われる。
嗚呼、そんなに僕の体温が欲しいなら一生抱き締めてあげる。
こんなに可憐な日鞠を見られるのなら、ずっと季節が冬で止まってくれて構わない。
「可愛い。」
「え?」
「僕の日鞠は本当に、可愛いね。」
僕は堪らず彼女の顎を持ち上げて、そっと口付けを落とした。
甘い甘い、蜂蜜の様な日鞠の唇。
砂糖が麻薬より依存性が高いなんて話を聴いた事があるけれど、日鞠の唇はそれを凌駕する依存性を孕んでいる。
「愛してるよ。」
ワンピースの裾から伸びる華奢な脚に手を這わせれば、僕達の混ざった唾液が光沢を放つ唇を開いて喘ぎ声漏らす可愛い彼女。
それだけで僕の理性はあっという間に突き崩された。
「私も…ひー君の事愛してる。」
潤んだ瞳で僕を捕らえ、促さなくとも「愛してる」と云う言葉を吐き出した相手に、僕は満面の笑みを浮かべた。
長い月日を要したけれど、日鞠が自然と僕に「愛してる」と云ってくれるようになった。
彼女の脳を、心を、躰を、僕はちゃあんと毒する事ができている。
愛しい日鞠の体温をいつも以上に感じられるのなら、寒さの残るこんな日も悪くない。
本日も、僕の彼女への「占脳」は順調だ。
Written by久遠氷雨(猛毒狂詩曲)
シェア
コメント
ログインするとコメントが投稿できます
まだコメントがありません